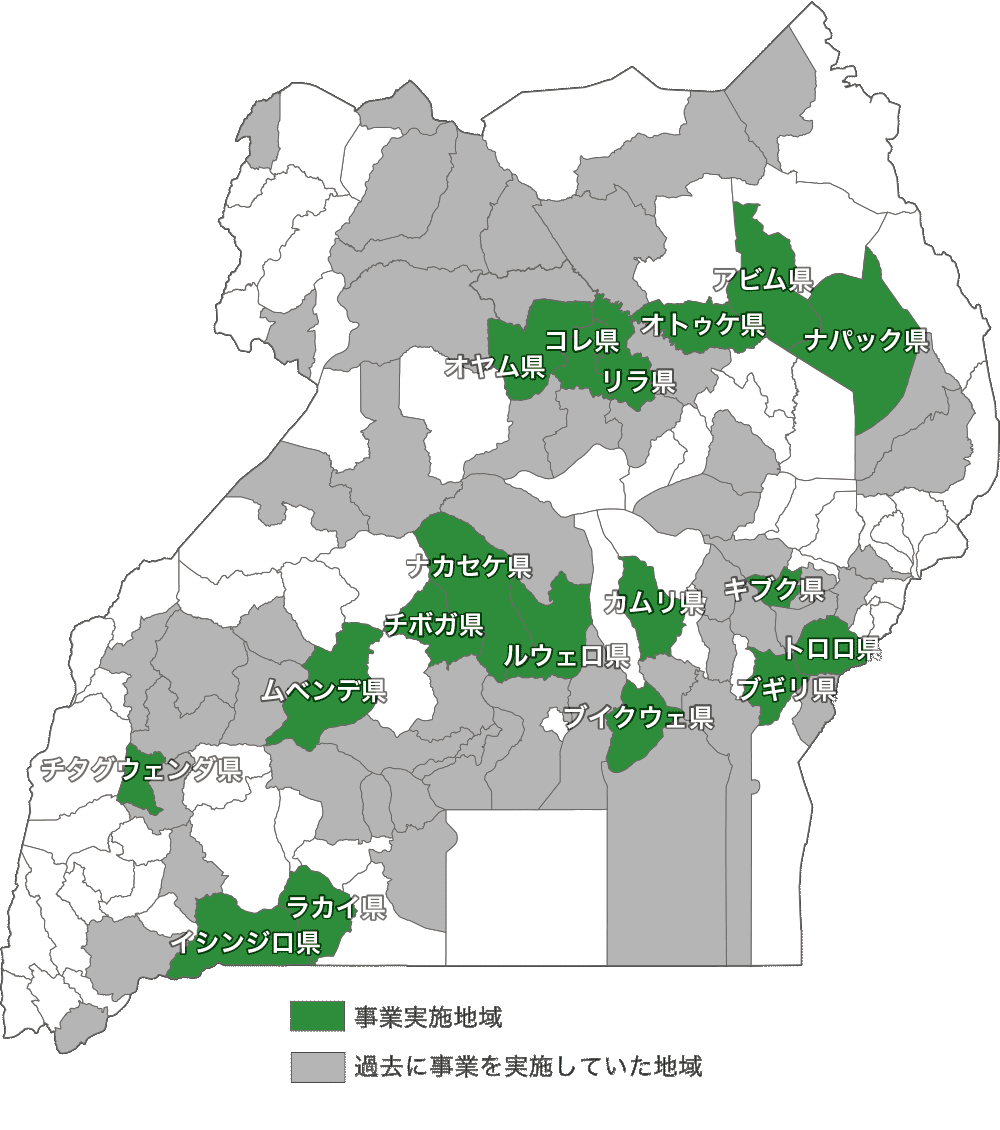

プログラムの対象農家
約 40,200人(うち女性24,285人)

研修を受講した普及員
158人(うち女性65人)

市場志向型農業の研修を受講した農家
25,200人 以上(うち女性15,154人)

対象農家の農作物収量(2021年比)
コメ 65% 以上増

普及対象の生物学的栄養強化作物
4 種類
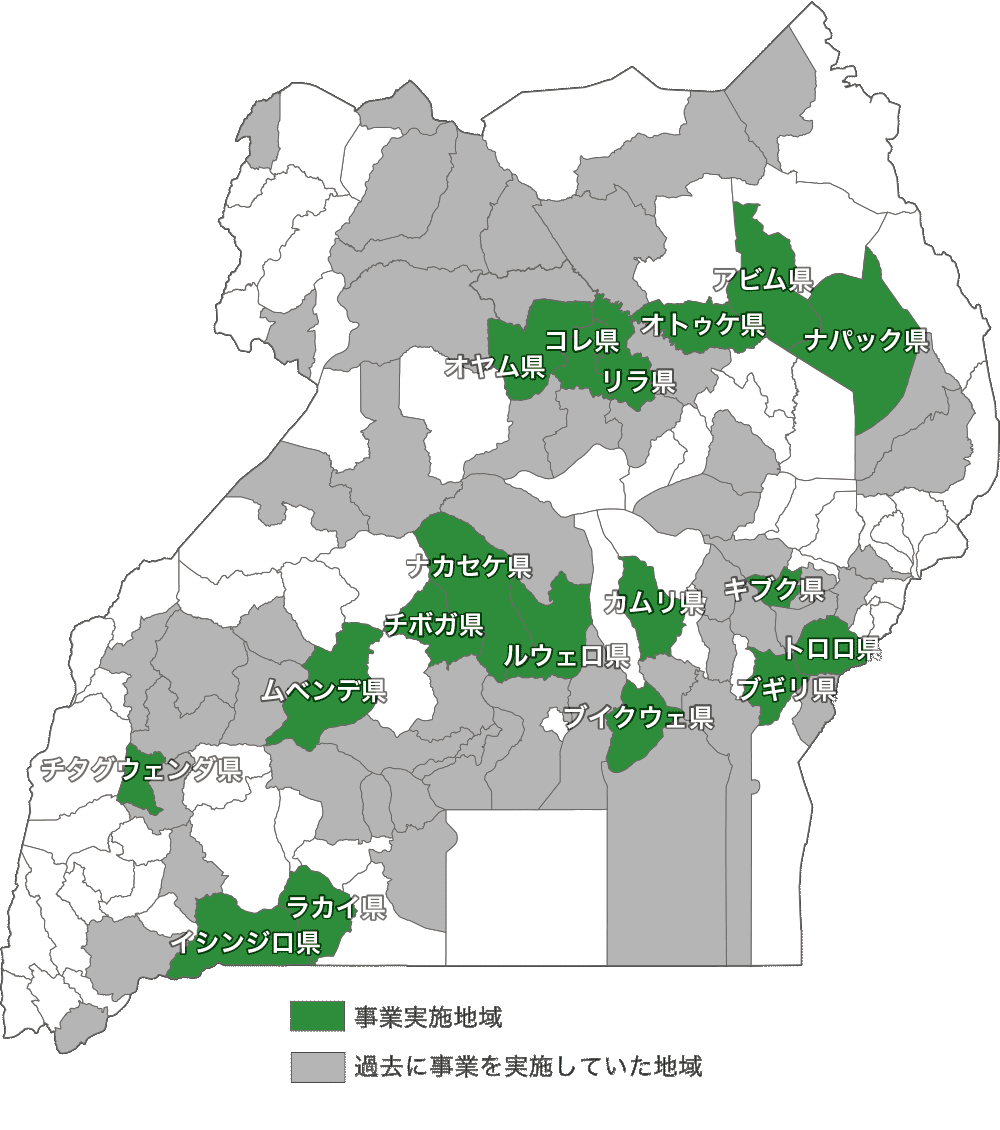

プログラムの対象農家
約 40,200人(うち女性24,285人)

研修を受講した普及員
158人(うち女性65人)

市場志向型農業の研修を受講した農家
25,200人 以上(うち女性15,154人)

対象農家の農作物収量(2021年比)
コメ 65% 以上増

普及対象の生物学的栄養強化作物
4 種類
ウガンダでは農業が人々の生活と経済の中心になっており、国民の大半が自給的農業と商業的農業の両方に従事しています。年間の平均気温が20〜30℃という安定した気候、肥沃な土壌、年2回の雨季といった好条件により多様な農作物が栽培されており、メイズ(トウモロコシ)、キャッサバ、プランテン(料理用バナナ)、サツマイモといった主食作物だけでなく、コーヒーや紅茶といった換金作物などの栽培も盛んです。その一方で、道路や灌漑設備などのインフラ、良質な種子や肥料といった農業投入材や新たな農業技術へのアクセス、気候変動リスクに対する脆弱性などの難しい課題も存在します。
このような課題に対し、ウガンダ政府はパートナー団体と協力して持続可能な農業技術の推進、農家に対する少額融資スキームの促進、農家を対象とした研修や資源の提供などを目的としたイニシアチブを始動しました。近年は、農産物の国内・外の市場における競争力を高めるため、付加価値の創出とアグリビジネスが重視され、農業は依然として農村開発と貧困削減の重要な原動力となっています。
笹川アフリカ協会(現ササカワ・アフリカ財団)のウガンダ事業は、ウガンダ農業畜産水産省との覚書に基づき1996年に設立されました。Sasakawa Global 2000(通称SG2000)として知られるこのプログラムは、設立当初から日本財団の支援を受け、小規模農家の食料安全保障と所得の向上を目的として、改良農業技術の普及を推進してきました。SG2000ウガンダは、地域で意識の高い農家をコミュニティ・ファシリテーター(Community Based Facilitator)として育成し、小規模農家に対する普及・アドバイザリーサービスの末端の担い手として活用することで、政府の農業普及システムを強化したのです。
2010年には組織戦略の刷新に伴い、SG2000ウガンダは農業バリューチェーンに焦点を当てることとなり、大きな変革を遂げました。農作物の生産性向上は引き続き優先課題となりましたが、同戦略では収穫後の管理や農産加工、市場連携の確立といった側面にも重点を置き、より総合的なアプローチが採用されました。農村部の若者の重要な役割が注目されたほか、特に女性に対するより包括的な助言サービス、農家組織の強化、市場アクセスの拡大、官民パートナーシップの支援も強調されることとなりました。
2021年、SG2000ウガンダはその名称を「SAAウガンダ」と改め、新たな5カ年戦略(2021~2025)を始動しました。この戦略はウガンダにおいて、より強靭で持続可能な食糧システムを支援することを目的とし、過去の実績を踏まえつつ新たな成果を追求しています。
こうした活動により、SAAウガンダは、2040年までに中所得者層の地位を向上するという政府の目標達成努力に貢献したとしてきたことが評価され、これまでにビジョナリー賞を複数回受賞するなど、農業政策に合致した活動の功績が評価されています。

SAAの活動は農業普及システムの強化を目的とし、官民の農業普及員や農家を中心とした農業バリューチェーンの全てのアクターを対象に、技術移転によるキャパシティ・ビルディングを実施しています。中でも、SAAの現地職員が普及員に研修を行い、研修を受けた普及員が農家を指導するカスケード式の技術・知識移転が特徴です。小規模農家に寄り添った持続可能な農業開発を促進するため、環境再生型農業・栄養に配慮した農業・市場志向型農業を3つの重点分野として、包括的な参加型アプローチを実現しています。ウガンダでは以下の活動を主に行っています。
2026年1月1日
2025年12月10日
2025年12月10日
2025年11月17日
| 期間 | プロジェクト名 | ドナー | 助成金額 | 対象地域 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-2018 | 植物油開発プロジェクト(VODP)フェーズ2 | ウガンダ農業畜産水産省 (MAAIF) | 初年度 Ugx 663,339,000 ($201,000) |
ジンジャ、イガンガ、カムリ |
| 2015-Todate | 生産者団体を通じた農民の市場アクセスの改善 | aBi トラスト | Ugx 1,130,094,000 ($342,453) |
ブイクウェ、ジンジャ、カムリ、トロロ、パリサ、ブギリ、リラ、カムウェンゲ |
| 2015-2019 | ウガンダ北部の農業普及とバリューチェーン開発 (ウガンダの成長プロジェクトの延長) | K+S フェーズ2 | €724,500 | ドコロ、アパッチ |
| 2014-2017 | 農業組織プロジェクト ※笹川アフリカ農業普及教育基金(SAFE)が実施 |
日本財団 | $572,771 | ルウェロ、リラ、ブイクウェ、ブギリ、カムウェンゲ、イガンガ、カムリ、パリサ、トロロ |
| 2013-2014 | ウガンダ北部の農業普及とバリューチェーン開発(ウガンダの成長プロジェクトの延長) | K+S フェーズ1 | €933,700 | ドコロ、アパッチ |
| 2012-2014 | P食糧安全保障と所得向上のための家族経営農業の促進とワン・ストップ・センターアプローチによる農民の市場アクセスの改善 | aBi トラスト | $340,000 | ブイクウェ、ルウェロ、ジンジャ、カムリ、トロロ、ブギリ、リラ、カムウェンゲ |
| 2012-2013 | 東アフリカにおけるソルダムのバリューチェーン開発プロジェクト | 農村開発のための欧州協同組合(EUCORD/EABL) | $50,504 | キェゲグワ、リラ、オヤム、アパック、コレ、ムベンデ |
横スクロールで全ての項目を表示出来ます
Sasakawa Africa Association - Uganda
Plot 12, Princess Anne Drive, PO Box 6987, Bugolobi, Kampala, Uganda
+256-41-4345497 / +256-393-261180

SAAの活動動向をレポートしたE-ニュースレターを隔月で発行しています。
E-ニュースレターの日本語翻訳版(PDF)はE-ライブラリーでご覧いただけます。

2023年度年次報告書(英文)がダウンロードいただけます。